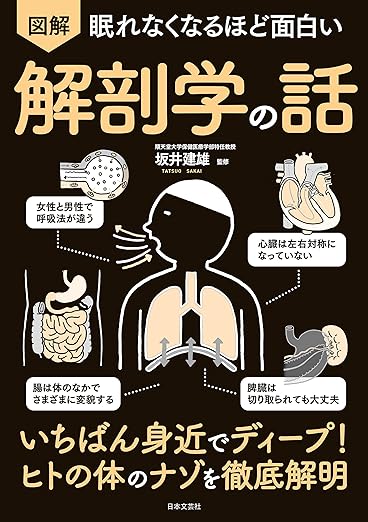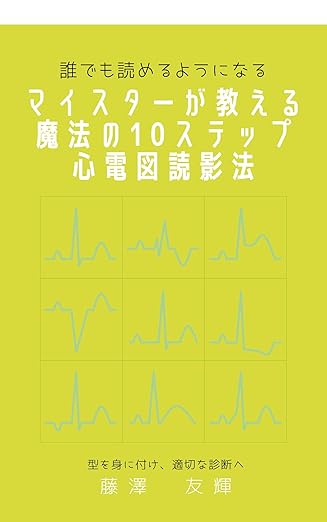千葉市消防局_救急活動時の救急救命処置による事故調査検証報告書
https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/shichokoshitsu/hisho/hodo/documents/220311-3-2.pdf
背景
- 救急救命士制度の概要: 救急救命士は医師の指示のもと、侵襲的な処置を行うことが可能。質の保証のためにプロトコールが定められています。
- 事故の発端: 令和3年10月3日、アナフィラキシー傷病者に対するアドレナリンの誤投与事故が発生。これを受け、専門部会が設置され、原因究明と再発防止の検討が行われました。
事故の概要
- 詳細な事故経緯:
- 救急車内で救急救命士がアドレナリンを静脈内投与し、その後、致死的不整脈により傷病者が心肺停止状態に。
問題点と原因分析
- 救急隊長のリーダーシップの欠如:
- 救急隊全体の指揮を取るべき隊長が適切に指示できなかった。
- 知識不足:
- 救急救命士がアドレナリンの正しい適用方法を誤解。
- コミュニケーションエラー:
- 医師との指示確認が不十分で、曖昧な指示内容が事故を誘発。
- 監督体制の不明確さ:
- 医師と救急隊の指揮命令関係が不明確で、誤解を招いた。
再発防止策
- 短期的な取り組み:
- アナフィラキシー患者対応手順の見直し。
- 救急隊と医師双方における知識・手順の再確認。
- 中長期的な取り組み:
- 救急隊長のリーダーシップ研修。
- 医師と救急隊のコミュニケーション改善。
- 救急活動中のモニタリング専任職員の配置。
結論と提言
- 事故は個人のミスではなく、システムの複合的な問題に起因。
- チームワークとコミュニケーション、リーダーシップの強化が必要。
- 再発防止に向けた組織全体の取り組みを提言。
以上報告書の要約ですが、気になるのは以下
検討事項7
救急業務実施報告書の記載内容について 公文書である救急業務実施報告書(救急活動記録票)の概要欄が、食後から呼吸が苦しくなったという事実の1行しか記載されていないという問題点が指摘された。本事案においては、「千葉市消防局事故処理マニュアル」に従い、消防署長から消防局長宛てに、詳細を記録した「事案報告書」を「救急業務実施報告書」とは別に提出しているとのことであったが、救急業務実施報告書の概要欄が簡略すぎる記載のため、救急隊長が同報告書を作成した時点では、事案の重大さをあまり理解していなかった可能性が残る。 なお、救急活動記録票の雛型は、平成14年に国レベルで作成されたが、当初の構想では、医療記録と同様に記載するという方針であった。東京消防庁においても、書面で救急活動の最初から最後までが読み取れる形で記載するよう指導がなされており、本事案においても、救急業務実施報告書は、全体像が掴めるように概要を記録するべきであるとされた。
消防庁ヒヤリハットデータベースをみてもわかるのだが、報告書を見ても何でそうなった?がわかりにくい文章となっている。
わざとしているのか?それとも国語力の問題か不明だが、活動記録は詳細に記載していた方が何かあったときに回答に窮することになるので気をつけましょう。